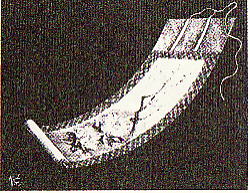| 武 蔵 野 (8p目/13pの内) 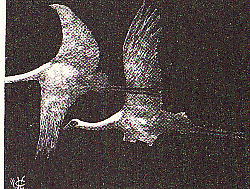 挿画 児玉悦夫 |
娘の母親から下宿先の主人を通して物言いがついた。 娘はまだこれから家事や諸芸を学ばせばならない年齢だし、日高もまだ学生だ。お互い将来にキズがつきかねないので、この際交際をやめてもらいたい。 娘には私から厳しく言いきかせて納得させたので、日高にはご主人からとくと注意してもらいたい。こういう話だった。 若者同士のことだからー。知人はそう思ったが、隣家の母親のあまりの剣幕に承知せざるを得なかった。 『いまは勉強が第一。細島の両親には内緒にしておくから交際はあきらめなさい』。 知人にいましめられて帰ってきたという。 日高の話を聞きおわって牧水の胸も痛んだ。彼ほどの恋の経験はないが、好ましく心に描いた女性はいた。日高の悩みはわかる。 『園肋やん。そんな馬鹿な話があるもんか。本人同士が一番だよ。おれが神戸に行ってその母親に会って談判してやるよ』 同情がたちまち義憤に変わった。日高の方が驚いて止めたが、牧水はいったん言い出したらあとに引かない気性だ。 同級生間では世話好きで通っているし、親分肌のところも大いにある。 折角細島港まで帰り着きながらそのまま次の便船で神戸に折り返した。 母親に無理に面会を求めて談判した。東京仕込みの恋愛至上主義みたいなことを自分では滔滔として述べたつもりだが、相手は微動だにしない。 『j日高さんのお気持も、あなたがおっしゃることもありがたいこととは思いますが、私どもには私どもの考えがございます。娘ももうその気はない、と言っておりますのでこれまでのことはきれいに水に流してほしい。日高さんには、親友のあなたからよく言い聞かせてあげて、若気のあやまちを起こさないようにさせてください』。 かえって牧水が日高の説得を頼まれる始末で終わってしまった。 初めの意気けんこうはとこへやら帰りはすっかり自己嫌悪に陥っていた。甲板に出て海風に吹かれても気は重かった。 日高も牧水の談判が成功すると信じていたわけじゃない。それでもいちるの望みを託していたものか、牧水が不首尾をわびると、 『いいよ、いいよ。繁ちゃん。おれも男じゃが。きっぱりあきらめるが』 強がりを言いながらも肩を落としていた。 牧水にはまことに不本意な神戸往復の船旅であった。 だが、人間の出会いとは不思議なものである。この日彼は終生忘れ得ぬ人に会っていた。 |