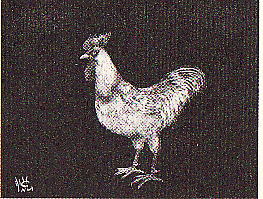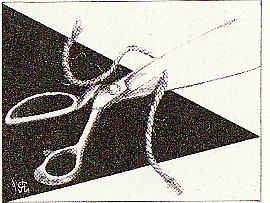| 小 枝 子 (7p目/19pの内) 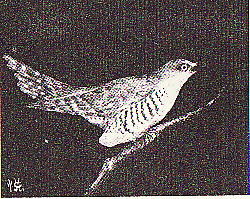 挿画 児玉悦夫 |
土岐潮友には将来を約束した恋人がいた。両方の家族も認めている仲だった。毎日のように恋人あての手紙をしたためていた。 高原の秋草の花を摘んで小包にして送る情の細やかなところも見せた。 ある夜、湖友が彼の恋人のことを打ち明けたあとで牧水に言った。 『若山君、妹の和貴が君を尊敬しているようだよ。もしよかったら付き合ってみてくれないか。気に入ってもらってでもくれれば、僕はもちろん、母や兄姉たちもきっと賛成してくれると思うんだがー』 真顔になってそう言う。牧水も真面目に好意を謝したが、彼にはすでに小枝子という愛する女性が存在した。 『僕のような田舎者では、和貴さんとは不似合だよ。それにどう暮らしを立てていくやら、将来の目当てもない身分だし:・』 ていよくその話を断わった。 そしてー人きりになると、東京の園田小枝子に手紙を書いていた。 彼はもう小枝子を自分の伴侶と定めていて歌にもそう詠んでいた。 大空に星のふる夜を火の山の裾に旅寝し妻をしぞ思ふ 火の山にしばし煙の絶えにけりいのち死ぬべくひとのこひしき そのうちに小枝子からの葉書が軽井沢に届いた。 『あなたと遠く離れて住んでいるのがさびしい。一日も早く東京に帰ってきてほしい』 走り書きの文面に牧水を恋うる切々たる思いがあった。 牧水も湖友も翻訳の仕事をしないのだから入金のあてはない。僅かばかりの所持金も底をつきかけていた。そこへ小枝子から便りがあったためすぐに軽井沢を引き揚げることにした。 商科の学生と、あと数日残る、という湖友に別れて牧水一人帰京することにした。 碓氷峠の中腹まで二人が送ってくれた。そこから一人峠道を登って行った。峠の茶屋あたりは一面の濃い霧につつまれていた。 わかれては十日ありえずあわただしまた碓氷越え君見むと行く 瞰(み)下せば霧に沈めるふもと野の国のいづくぞほととぎす啼く 碓氷をくだり、坂本の宿に泊り、妙義山を見て東京に帰り着いたが、数日間、離室にいただけで今度は名古屋に出向いた。八月九日のことだ。 この年の三月に名古屋在住の歌人らが短歌雑誌『八乙女』を創刊している。牧水もこの雑誌に投稿していた。 『八乙女』同人らの誘いで彼らの歌会に顔を出したのだった。 |