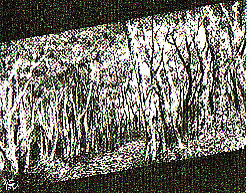| 病 む 日 (7p目/16pの内)  挿画 児玉悦夫 |
麹町まで往復したのがたたったものか、翌日はどうにもならぬくらい足がだるい。終日鈴木方で寝ころんでいた。 朝からオルガンが聞こえてくる。二階の窓から見ると、隣家の小学生らしい女の子が弾いているのが開け放ったガラス戸の奥にのぞかれる。たどたどしい調べが、かえって隣家のあたたかい家庭をほほえましくしのばせる。 この日も来信が多かった。海野からも届いた。これは昨日の返事ではなく多分鈴木方に落ちついているはずと察して出したものだ。 『二十八日ごろまで滞在する』とある。『人の子』も一緒らしい。 猪狩白梅からも病状を問い合わせてきていた。玉蔵院で別れた関謙三からの手紙が思いがけずあったのはうれしかった。 神戸の長田の叔母からは浴衣を送ってきていた。 海野が殊勝にも『早くも初秋の気配の軽井沢のにはひを-』と、同封していた女郎花の押花を日記にはった。 人のぬくもりをしみじみ感じた。 都農の河野からこの日届いた三円の為替もいつもよりあたたかいように思えた。さっそく礼状をしたためた。 ~酷暑の候、御無事の由、大慶至極に存じ奉り候。小生の病勢、どうも思うやうにまゐらず、腹が立ってたまらず候。昨日、杏雲堂の佐々木博士に診察を乞ひしに、脚気は重くはなけれど、急には全快せざるべく、脳は養生次第では早かるべしとの事に候ひき。 本日御送付下され候金三円、正にありがたく拝領仕り候。今日の場合、べつだん嬉しく存じ申し候。 杏雲堂病院は坪谷出身の富山しげが看護婦をしている。彼女の母山口マスから、葉山滞在中に手紙をもらった。 『-東京のようすはちっともわからないが、繁さんが近くにいると聞いて安心している。どうぞしげを頼みます』 とあった。そのこともあって杏雲堂をたずね、しげのすすめで診察してもらったものだ。脳は神経症のことに過ぎない。 佐々木博士は心配ない、と診断してくれたが、調子はよくない。足の指先までしびれるようなので諏訪町の坂口観成堂病院に行った。 診断は似たり寄ったりで、薬をくれた。診察料、薬代合わせて二十四銭。痛い出費になった。 しばらく通院した方がいいーと言うので翌日も行った。二時間持たされて薬をまたもらって帰った。あくる日もまた-。 薬の効能も疑わしいし、出費が恐ろしいのでまた玉川に転地することにした。 |